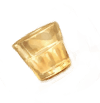六月のリトマス試験紙
中原まなみ
それはとっておきの宝物の場所を教えるみたいな声だった。
「ねぇ。もうすぐ世界が終わるんだよ」
少しだけ恐ろしげに。少しだけ悲しげに。でも、たっぷりの楽しさを隠そうともせずに。
「世界?」
あたしは読んでいた本から顔を上げて、軽く首を傾げた。夏鈴はふわりと微笑むと、明るい茶色の髪を揺らしながら寄ってきた。細い指が、あたしの真っ黒なショートヘアを撫ぜる。
「そ。世界」
言いながら、夏鈴があたしの髪を撫ぜているのとは反対側の手で、あたしの本を閉じようとする。あたしはそっとその手を抑え込む。
「やめてよ。まだ読んでるんだから」
「やだ。おしまい」
「おしまいじゃないよ」
「だって
ぷう、と音を立てそうなほど分かりやすく頬を膨らませて、夏鈴が不満げな顔をしてみせた。
「せっかく一緒にいるのに」
「だって、今日はうちでゆっくりしたいって言ったの夏鈴じゃん」
「そだよ。ゆっくり、いちゃいちゃしたかったの」
言いながら、夏鈴がそっとおでこを近づけてきた。こつん、と軽くおでこが触れ合う。
「――あまえた」
「そだよ。知ってるでしょ」
くすくす、と夏鈴が笑った。
窓越しの雨音が、静かに染み渡ってくる。