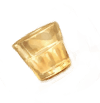妖精カンテラ
きりしま志帆
その日そのとき、俺は懸命に空を駆けていた。強い向かい風がしきりに行く手を阻んだが、背中の羽をチリチリ鳴らしながら一心に前へ進んだ。
速く、速く。もっと速く。
気持ちはいくらでも先行したが、里はいっこうに見えてこない。
「この羽はなんでこうも使えない!」
無駄に両手で空をかきながら、俺は役立たずな背中のものを罵った。
薄く透き通ったこの羽は、本来は滑空するためのものであって飛行するためのものではない。だから横の移動には不向きである。そんなことは分かっていた。
しかし、マツの葉のような脚でどれだけ懸命に走っても、やつらの脚には到底かなわない。もどかしくとも今は、この薄い羽を死に物狂いで動かして、一刻も早く仲間たちの元に帰らなくてはならなかった。
闇浮かびの森の奥深く。清らかな水が湧く沢の近く。いっとう大きなクヌギの木の下あたりが、俺の住んでいる里だった。
木のうろや岩陰に板をはめこんで住居を造り、男たちが採集する果実や木の芽を分け合って食べ、女たちが蔓を裂いて織り出した布で身を飾る――古来より自然とともに暮らしてきた、慎ましくも美しい里――だった。少なくとも、今朝までは。
しかし今、まばたきを忘れた俺の目には変わり果てた里の姿が映っている。
里のシンボルである大クヌギは根元がえぐれ、広場は無数の巨大な足跡ででこぼこになっていた。子どもたちが好きなスイカズラのブランコは引きちぎられ、原型がない。家という家は壁をこじ開けられ、中がめちゃくちゃに破壊されている。仲間の姿はない。誰ひとり――親代わりの長老も、友も、結婚を誓ったかわいい恋人も――誰ひとり。
「くそ――」
俺はその場に崩れ、握りしめた両のこぶしを強く地面に打ちつけた。
これが何の災いか、俺にはよく分かっていた。人間の仕業だ。花を探して森を歩いているさなかに、俺はその声を聞いていた。低い声がいくつもしていた。だから飛んで帰って来たのだ。それまで採集していたものを全部捨て、羽をボロボロにしながら、それでも全力で帰って来た。帰って、来たのに――。