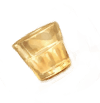薄明にも見えない光
作楽シン
気がつくとカビっぽい臭いに包まれていた。薄汚れたベッドに横になっている。
家の中になんて、ましてやベッドになんていた記憶がない。あたしは森を抜けて町に向かっていたはず。
一体、何がどうして。――眩しい。
薄いカーテンだけがしめられた窓から夕日が差し込んでくる。あたしは手探りで、いつもかぶっているキャスケットを探した。枕元においてあったそれをかぶり、すぐに自分の隣を確認した。
青白い顔の少年が目を閉じている。心臓が飛びはねて、そのまま早鐘を打った。
「ベンジー! ベンジャミン!」
呼びながら揺さぶる。金色の睫がふるえた。目を覚まさない。だけど、ホッとした。――生きてる。
深く深く息を吐いてから、揺さぶるのをやめる。
「道ばたで倒れてるのを見つけたの。森からでて、何もないところよ。ここまで運ぶの大変だったわ」
突然声が聞こえて、ホッとしたのも束の間、あたしは飛び起きた。眠ったままのベンジーを後ろにかばうようにして、声の方を見る。
埃っぽい部屋の中は薄暗い。あたしより少し年上くらいの女の人が、ベッドの近くで椅子に座っていた。ブルネットの長い髪を三つ編みにした女の人だった。
「あんたたち、どうしてあんなところで倒れてたの?」
「わからない」
そんなわけないでしょ、と女の人の眉がはねあがる。
「どこに向かっていて、何をしようとしていて、どうして倒れたのか。一個ずつ聞かないと答えられない?」
冷静な声が淡々と問う。
あたしは、そっと息を吐いた。道ばたで倒れて、この人に拾われて、知らない家で目覚めた。いい状況なのか、よくない状況なのか、分からない。だけど大抵は、よくない状況だ。
でもベンジーはそばにいる。あたしは慎重に言葉を探した。
「あたしたち、街に食料を探しに行ってたとこだったの」
「……そう」
「たどり着く前に疲れて倒れちゃったみたい。お腹がすいて」
華奢な体に、汚れたシャツとジーンズをまとった女の人の目は、ただただじっとあたしを見ている。少しの嘘もごまかしも許さない、あたしの言葉は何も信じない、とでも言うかのようだった。