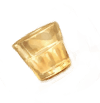ノアとイヴの100ヶ月
だも
ああ、また死なせてしまった。そんなつもりはなかったのに。
私は鳥の死骸を胸に抱いて、浜辺でそっと立ち上がった。
「愛情をかけたぶんだけ応えてくれるわ」
「毎日話しかけているの、植物だって人の言葉がわかるのよ」
「いい子だぞ、アレックス。ほらご褒美だ」
モリスもキッカスもジンも、みんなみんな愛情の対象を持って日々を過ごしているというのに、わたしだけがうまくいかない。いつも死なせてしまう、この浜辺に流れ着く小さな命たちを。
「ねえ、マーラン。わたしのなにがいけないのかしら? なにが間違っているのかしら?」
お墓作りを生業にしているマーランは、死者にさえ愛情をかけている変わり者だ。けれどもいまは新しく穴を掘るのに夢中になっているようで、ざくざくと土を起こす音と彼の鼻歌が切れ切れに聞こえるだけだった。
仕方なくわたしも浜辺から離れて穴を掘る。少し湿った泥土は、黒く私のうでを汚す。横たえた鳥から鮮やかな緑の羽根をひとつ抜き取り、かぶせた土に挿して墓標にした。まわりには似たような盛り上がりが大小たくさんある。これらすべて、わたしが死なせてしまった命たちだ。おばあさんのもの以外。
そのとき、なにか鈍い音がした。
あまり聞いたことのない種類だったので、わたしは周囲を見渡して耳を澄ませた。どちらから聞こえてきたのだろうと考えているうちに、男のもがく声に気がつく。アダムだ。最近、イヴにしょっちゅう愛をささやいていたのですぐにわかった。
「アダム? アダム、大丈夫?」
私は彼に向かって声をかける。けれどもとても返事ができる状況ではないらしい。私は耳をすませ続けた。水のはねる音もアダムの声も聞こえなくなると、歌が聞こえてきた。イヴだ。弔いだろうか、その旋律には覚えがあった。ずっとずっと昔におばあさんが歌ってくれたし、みんなも時々歌っている、とても短くて、心が鎮まる、そんな旋律。覚え違いなのか、イヴが繰り返すその歌には一音足りないようだった。
楽譜が刻まれた版が、家にある。
やがてそれさえも聞こえなくなると、海の向こうに太陽が落ちて真っ暗になった。