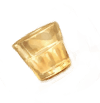死後に生まれるチャーリー・クレイの物語
千葉まりお
チャーミング。
父の人となりを伝えるのにこれ程適した言葉はありません。まさに父のための言葉です。そうでしょう?
私の父、チャーリー・クレイは何に対しても「これ以上美しいものは見たことがない」という顔で笑う人でした。
三つの川に囲まれたこの丘の町には美しいものが沢山あります。春は川辺で戯れるチュウシャクシギ。夏は空に高く上がる色とりどりの凧。秋は丘を埋め尽くすマムズ。冬は家々を飾るイルミネーション。誰もが思わず笑顔になる美しいものです。
しかし父は道端の雑草や、薄汚い鳩、破れたビニール袋などの、私が意識の外に追いやっている物にもシギやマムズを見つけた時と同じ微笑みを向けました。まるで川底の泥から一握りの砂金を掬うように、父は打ち捨てられた物からそれ固有の美しさを見つけ出せる人だったのです。
父が笑うと、ただでさえ丸いあの顔が一層丸くなり、エクボが二つ、控えめなクレーターのように頬に現れました。
母は父のこの笑顔を「お月様」と呼んでいました。「今日はいいウィスキーを頂いたから、お月様が出てきそうね」とか「元気がないわね。お月様を見てきたらどう? 今ベランダにいるわよ」なんて風に。
私は子供の頃から父のお月様に支えられてきました。どんなに自己嫌悪に苛まれている時でもあのお月様に微笑まれると「自分はとても素晴らしい存在なのかもしれない」と勇気付けられるのです。
父は母にとって良き夫であり、私の妻にとって良き相談役であり、私の娘達にとって良き祖父であり、皆さんにとって良き友でありました。
それに酒場では礼節を守りながらウィスキーを楽しむ、良き客でした。
父は酔うと片方の目──決まっていつも緑色の方の目でしたが、そちらを閉じ、菫色の目だけを開けて誰もいない空間に話しかける癖がありました。
独り言は独り言なのですが、本当にそこに誰かがいるように話すので、幼かった私は父の視線の先に誰かがいるように感じ始めました。
子供の思い込みの力は凄いもので、その内に私は誰も座っていない椅子に女性の姿を見るようになりました。ある種のイマジナリーフレンドというやつですね。彼女の顔がどこか父に似ていたのと、父と同じく左右で色の違う目をしていたのは、子供の想像力の限界ゆえでしょう。