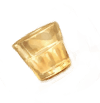雨の終末に船を出す
冬木洋子
『ガガッ……ニュースをおつたえ……午後……頃……二丁目一帯……水没し……た……』
古ぼけたラジオが眠りから覚めたように鳴りだして、かわりばえしないニュースを雑音混じりに伝えてきた。
ぼくはくしゃくしゃになった煙草の箱を手に、ぼんやりと壁にもたれたまま、見るともなしに窓の外を見る。
今日は天気がいい。
というのは、雨脚が少し弱いという意味だけれど。
もうずっと、雨が降り続いている。きっと、世界の終わりまで降り続く雨。
たいていは静かに、霧のように世界を包み、ときには激しく窓を叩き、ひとときも止むことがない。
雨が降っていない状態というのがどういうものだったのか、もう、忘れかけている。
『ガガガッ……くりかえしま……本日……時頃……町二丁目……水ぼ……ガガガガガガガガガ……ッピーーーー』
けたたましいハウリング音に顔をしかめて、ぼくはラジオの電源を切った。このラジオも、もうそろそろ駄目かもしれない。
そもそも、なぜこんな古めかしいラジオがここにあるのか、わからないのだ。最初からこの部屋にあったという憶えも、自分が持ってきたという憶えもないのに、いつのまにか机の上にあって、ときおり思いだしたように雑音混じりのニュースを勝手に伝えてくる。かつては、途切れ途切れの古い歌や、無線が混線しているのか他人の会話の断片が流れ出すこともあったが、今はもう、淡々と、各地区の水没のニュースを伝え続けるだけだ。
そのニュースだって、いつまで続くかわからない。
ラジオの電波は、きっと、窓から見えるあの高い塔の上から来ているのだろう。天を衝くように聳え立って街を見下ろす錆びた鉄塔の上から。誰かがそこで、沈みゆく世界を観測し、何のためかはしらないが、街の人々に伝えているのだろう。
けれど、あの塔だって、いつまで崩れずにあることやら。
ぼくは窓を開けて、ラジオを遠くに投げ捨てた。
どこが水没したかなど、どうでもいい。ぼくには関係のないことだ。
毎日のように、街のそこここが前触れもなく崩れて、水没してゆく。ときおり、遠く近く、崩壊の波音を聴くこともある。崩れ落ちた街は、ただ水の底に沈むのではない。虚無に落ち込んで、その街区があった空間そのものが、跡形もなく消えてしまうらしい。世界の虫喰いのように。