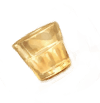おいしくめしあがれ
塩
――私は人間である。名前はもうない。
行き詰まった文の端、ざらりとペンを走らせれば、まるで咎めるように扉が鳴った。爪の先で表面を弾くだけの、ノックというには遠慮がちに過ぎる音。扉が控えめに開き、深い黒の外套に身を包んだ背の高い青年、私のあるじが顔を覗かせる。吹雪の匂いのする髪からこぼれ落ちたひとひらの雪は、床に着くのを待たずに消えた。
昇華した氷の行方を追いかける私の耳に、弦楽器のような声が降る。見上げれば、白皙の美貌の中、静寂を色にしたような切れ長の目とあって、私は仕方なく外していた首輪を接続した。象牙色の作りものめいた唇が、もう一度、チェリストのように歌う。謎めいた音楽は私の首元で電子音声に変換され、ようやく言葉に結ばれる。
『出かけるよ』
はい、と私は答える。首元から音楽が鳴る。むずがゆさに手をやると、ぎぃっと低い声が降る。電子音声が鳴る前にわかる。『だめ』、警告音だ。
『今は外さないで』
首元から電子音声が言う。首輪のようにも見えるこれは、翻訳機だ。精度は微妙だが、それでも日常会話程度ならば繋いでくれる。あきらめて首から手を離せば、細められる睫毛はしろがね、凍てついた樹氷のようで、私は目をまたたく。見慣れた今でもふとしたときに、そのうつくしさに息を飲む。そしてそのたびに自身に警告する。ぎぃっと軋むような音を、頭に何度でも響かせる。
人外だぞ、と。
――夢にまで見た人外さまなんだぞ人の姿しかないけど。異類婚ものの夢小説かよごちそうさまですでも自分には萌えねえので主人公他に連れてこいむしろ現実が来い!
一瞬、眼差しの遠ざかった私を手招いて、エスコートのように差し出される手のひら。彼の血は赤いのだろうか。もしかしたら象牙色をしているのかもしれない。赤い血の流れるはずの自分の手のひらを見下ろす。人形のように整った手に重ねることはせずに、あるじの後ろに立つ。ちらりとこちらを見た後、あきらめたように歩き始める背を追う。
今日の書き物はぜんぜん進まなかった。きっと帰ってからも、一文字だって書けることはないだろう。私はそっとため息を落とした。