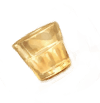Killing me
望月あん
目覚めるとき、世界はいつも停止していた。
いまにも横転しそうなままぴくりともしない大型トラックの影から、ヘルメットを被った男が這い出てくる。ヘルメットの塗装は裂かれたように剥がれて、腹には金属の破片が突き刺さり、コットンの白いシャツと淡いデニムは血に染まっていた。後方にはバイクの残骸が散らばり、油やタイヤの黒ずんだ軌跡が足もとまで続いていた。彼は血まみれの自分の器を見おろして、どうやら車に巻き込まれたらしいと理解する。
破片を引き抜き、留め具の傷んだヘルメットをどうにか脱いで、彼ははあっと大きく息をついた。時が止まった街には、彼のほかに人はない。人だけではなく、動物や鳥や植物の姿もない。世界には無機物だけが取り残されていた。
視界の端を、雨粒のように小さな青いものがよぎる。降ってくるのではなく、舞いあがっていく。薄曇りの白い空を見あげると、ソーダ水を注いだコップの底にいるようだった。彼は両手に持っていたヘルメットを路上へ置いた。指が離れた瞬間から表面には青い泡が浮き上がり、離れ、ヘルメットは輪郭を残して光に透けていった。彼は泡をひとひら、潰さないよう優しくつかまえる。そっと手をひらくと泡はほのかに光りながら浮遊していた。いつか彼女がこの世界でいっとう美しいとこぼしたことを思い出す。そうやって世界を見つめる彼女の眼差しこそ、彼にはなによりうつくしかった。
じりりり、じりりんと、静寂を破って電話の呼び出し音が鳴る。歩道に停められた自転車のかごに黒電話があった。そちらへ向かって歩きながら、彼はまた目覚めてしまったことを静かに受けとめていた。もう何度目かしれない。数えることもやめてしまった。なぜ停止した世界で目覚めることを繰り返すのか考えることも、ずいぶんむかしに諦めてしまった。運命に抗ったところで、こたえを求めたところで、得られるものはなく虚しさが募るだけだった。いまはただ、世界がふたたび動きだすまでの短いときをせめて穏やかに過ごせるよう願っていた。
黒く冷たい受話器をあげる。ハロー、ハローと呼びかけると、レコードに針を置いたときのような雑音が届いた。それは次第に明確な音となり、言葉になる。