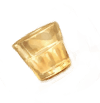水の星から来た
碧
女の徴がきた日、ヤクヌディは夢を見た。
それは、水に沈んでゆく夢で、それが水に沈んでゆく夢であることに気づくまでに、ヤクヌディは「陰の家」で夜を二度、過ごさなければならなかった。
雨季を迎えたばかりの村の空気は、湿り気を帯びて重くなっていた。日がな一日太陽の光を避けていると、ほんの少しだけ、肌寒さを感じる。ヤクヌディは寝ころんだまま、股から流れ出てきた赤黒いものに、足で砂をかける。砂もまた、湿り気を帯びていた。踏み慣れた固く乾いた土とは違う感触に、ヤクヌディはため息をつく。
女の血は穢れであり、月のものが来た女は、集落から離れて過ごさなければならなかった。それはユルグが犯した罪の証しだからだ。同時にまた、女の血は、大地に恵みをもたらす予感でもあった。ユルグの罪の償いであり、この大地の始まりとなったからだ。ユルグの血は大地を赤に染め上げ、そして、実りをもたらす。それが、世界の始まりだった。それゆえに、初めてそれが訪れた女は大いに祝福されるのだ。ヤクヌディも、この日が訪れることをずっと心待ちにしていた。そして、ヤクヌディの初潮は、他の女よりもいっそう特別だった。十四年の間、村中のすべての者がそれを心待ちにしていた。ヤクヌディは特別な娘だった。それは、幼い頃から
だのに、この二日というもの、ヤクヌディはずっと陰鬱な気分に支配されていた。それは初めて感じた異様な身体のだるさや、腹の痛みとは無関係だった。薄暗い「陰の家」の中で、過酷な労働を免除される無為な時の流れの中で、ヤクヌディは、初めて女の血を見た日の夢を反芻する。奇妙な夢だった。生ぬるい空間で、全身を柔らかく締め付けられるような、不思議な感覚に包まれていた。夢の中で、ヤクヌディは呼吸ができずにもがいていた。そこに大地はなかった。足をどこにもついていないのに、ヤクヌディは落下することもなく、その奇妙な空間に「漂って」いた。漂う。まるで雨季の終わりに時折見られる、植物の綿毛のように。